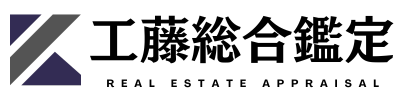前回、「不動産の収益性からの検討」において収益性からのアプローチの重要性について述べてきました。今回のテーマは、その「収益性からの検討を怠った場合の失敗例」についてふれていきます。
前回のおさらい
不動産の鑑定評価においては、基本的に①費用性、②市場性、③収益性の三つの視点から求める方法があり、昨今の投資対象の範囲の拡大によって収益性からのアプローチの重要性が高まっており、今日の不動産市場において収益性からのアプローチを抜きにして不動産の鑑定評価を行なうことは困難な状況も増えています。
ところで不動産の収益性からのアプローチを行なわずに済むような場面とはどのようなケースが想定されるでしょうか?
つまり、不動産にかかる市場参加者があまり収益性を重視することなく、費用性や市場性等を重視して意思決定を図るような市場における不動産とはどのようなものがあるのかということです。
これには前回述べた戸建住宅、分譲マンションや賃貸用に向かないような店舗、工場等が該当します。このような不動産は、法令上鑑定評価が要請されているような場合や交渉上、或いは、証拠書面として評価書があった方が有利に物事を進めやすい等の理由のほかは、特段鑑定評価が必要ないのかもしれません。なぜなら、不動産鑑定士に頼まなくてもある程度、概算で査定できてしまうからです。
しかしながら、不動産の収益性からのアプローチを行なうには、費用性や市場性からのアプローチに比べ、やや複雑になる場合も多く、収益性からのアプローチに精通した専門家の判断が必要とされる局面といえるのかもしれません。
不動産の収益性からの検討を怠った場合の失敗例
以下、不動産の収益性からの検討を怠った場合の失敗例についてご紹介していきたいと思います。この失敗例については、少々専門的な内容を含みますので、難しいと感じられた方は、最後のまとめの箇所のみ目を通していただければと思います。
【ケース1】現行地代が割高なため、借地権付建物全体としての収益性が劣る場合
対象不動産は、借地権に基づき建物が建築され、建物は賃貸借されていますが、現行地代が対象不動産の実力に比してあまりにも高いため、借地上の建物を賃貸借し、家賃収入が得られたとしても到底割に合わないケースです。
この案件は、企業が売買契約によって対象不動産を購入する際に借地権価格の求め方に問題があったため、売買契約成立後に保有する不動産を財務諸表にのせる段になって、鑑定評価を依頼され問題になりました。
つまり、売買契約時には、更地価格に相続税路線価の借地権割合を参考に対象不動産の借地権割合を求め、これを更地価格に乗じて借地権価格を求めていたようです。世間一般では、借地権価格を求める際に相続税路線価の借地権割合を用いて求めることは少なくありませんが、この相続税路線価の借地権割合はあくまで借地権割合算定の参考とする割合であって、対象不動産の契約内容、例えば、現行地代と対象不動産の実力に見合った正常な賃料との関係、一時金が支払われていれば、その金額や種類等といった個別的な事情をほとんど全くといっていい程、考慮しないものです。
このケースでは、どのように賃貸経営を改善したとしてもカバー仕切れないくらい、現行地代が高く、土地の賃借人は、土地を借りれば借りるほど損失を生んでしまう借地権付建物のケースです。さらにこのケースで問題だったのは、賃貸借契約により契約期間内の解約は多大な違約金を支払わなければならず、期間内の解約が実質的に困難な契約内容になっていました。
このような場合には、借りれば借りるほど土地の賃借人(=借地権付建物の所有者であり、建物の賃貸人)の損失が大きくなるため、例えば、年度ごとの損失分を現在価値に割引き、合計したものが土地の賃借人の経済的損失ということになり、これを借地権価格の鑑定評価において考慮する必要があります。
なお、この場合、被害を最小限に留めるには、賃料改定の交渉を行なうこと等も考えられますが、関係当事者は交渉に要する時間や労力等相当程度、覚悟しておく必要があります。
【ケース2】経営状態が良好な事業用不動産の場合
対象不動産は、自用の事業用不動産で経営成績は極めて良好でしたが、事業会社の資産圧縮のため、対象不動産を売却し、所有者がそのまま賃借人として借り受け、運営(=リースバック)することになったケースです。私が依頼を受けた段階では、売買当事者(=このケースでは、賃貸借当事者でもあります)間では既に売買契約が成立した後、さらに現賃貸人から第三者へ売却する場合の鑑定評価です。
このような場合、まず、賃料設定にあたり、現運営者の損益状況を分析して、現運営者の稼得した利益の中からどのくらい不動産に負担することができるのか、売買により現所有者が賃借人として借り受け、運営することになった場合の支払可能賃料等を査定した上で、対象不動産の収益性からのアプローチを行なう必要があります。この場合の賃借人の負担可能な支払い賃料を査定する際には、考慮しなければなりません。
この事例の最大の問題点は、原所有者(リースバックされる前の最初の所有者)は、事業により大きな収益を上げ、賃料負担力も十分に有していたにもかかわらず、事業収益に基づく収支分析を行なわず、リースバックによる賃貸借当事者間で明らかに低廉な賃料設定を行い、新所有者(=賃貸人)に低い価格で売却してしまったことです。賃貸人は、賃料設定が低いために獲得できたはずの賃料収入を得られず、その結果、売買価格も低くならざるを得ません。
まとめ
以上は、不動産の収益性からの検討を怠った場合の失敗例として、①現行地代が割高なため、借地権付建物全体としての収益性が劣るケース、②経営状態が良好な事業用不動産のケースを紹介しましたが、いずれも対象不動産の価値を求める際に、明らかに収益性からの適切なアプローチを行なっていないと考えられるケースです。契約を締結する前に、もし不動産の収益性からのアプローチを適切に行なっていれば、損失を被ったり、あるいは、利益を逸失することも回避できたはずなのに、貸借対照表に載せる段になって、あるいは、さらに売買した後になって初めて対象不動産の真の価値に気づいたという方がおられるのも事実です。
不動産の適正な価格や賃料を取引市場等で把握できるならば、法令上、鑑定評価が必要とされる場合や交渉上、鑑定評価が要求される場合等を除き、鑑定評価は必要ないのかもしれません。逆に言えば、たとえ法令上、或いは、訴訟上等において鑑定評価が必要なくとも対象不動産の適正な経済価値を求めるためには、不動産の鑑定評価が必要な場面もあるということです。
不動産の収益性からのアプローチを行なうことは、不動産の鑑定評価の中でも奥が深く、難しいジャンルの一つです。一般の人々にとって不動産の適切な価格や賃料を知ることが困難な場合、損失を被る、または、利益を逸失する前に時として不動産の専門家の意見や判断に頼ってみることも有力な選択肢の一つになるのではないかと思います。
次回は、土地の新規の賃貸借契約における賃料(=新規地代)の鑑定評価についてご紹介したいと思います。