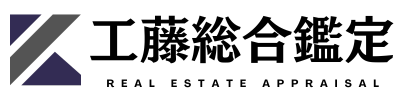前々回、借地権の鑑定評価-応用編として事業用定期借地権の鑑定評価について触れました。今回は、借地権の鑑定評価及び借地権と底地及び更地との関連についても触れていきたいと思います。
借地権の鑑定評価
実務上、借地権のみを評価の対象として依頼を受けることは少なく、借地権付建物として依頼を受けることの方が圧倒的に多くありますが、ごく稀に借地権を単独に評価してほしいという依頼を受けることがあります。実は、借地権付建物として依頼を受けた場合、これが収益性からのアプローチを行なうことが可能な不動産の場合、借地権価格を求める手法を割愛して評価を行なうこ場合もあるため、より適正な価格にアプローチするという観点から見れば、借地権のみを評価対象とする場合のほうが、借地権付建物を評価対象とする場合よりも難易度が高くなります。
難易度はさらに上がりますが、内容はさておき、話の流れを中心に抑えていただければと思います。
借地権と底地と更地の関係
まず、一般論として、更地、借地権、底地の間には次の関係が成立します。
(原則)
更地価格≧借地権価格+底地価格
更地価格>借地権価格
更地価格>底地価格
しかしながら、例外的に
(例外)
更地価格<借地権価格+底地価格
あるいは、
更地価格≦借地権価格
更地価格≦底地価格
となる場合もみられます。
原則的なケースについては直感的には理解できるかと思います。
では例外的なケースについてはどうでしょうか?
【設例】更地価格≦借地権価格となるケース
やや直感的な説明になりますが、土地の賃貸借契約において、普通借地権(旧借地法上の借地権を含む)東京銀座で地代が極めて低廉で公租公課よりも安い場合でかつ、当該、地代水準が長期間契約改定されることなく維持されてきた場合を想定してみます。このような場合、当初の契約当事者間の関係、経緯等諸事情を考慮する必要はありますが、更地価格≦借地権価格は高くなる可能性が高くなります。
すなわち、賃借人にとって土地を所有し、固定資産税等を払うよりも地代を払い続けた方が得だと考えられるからです。ただし、この場合、賃料改定のリスク、解約リスク等による賃料差額の持続可能性等を十分に検討する必要があります。
これを具体的に検証するためには、直感的な理解はいうまでもありませんが、最終的には最低限の数学的な素養が絶対不可欠です。
【設例】更地価格≦底地価格となるケース
このケースについては、弊社ブログ令和5年(2023年)12月28日付の「不動産の収益性からの検討を怠った場合の失敗例」で述べた設例になります。
このケースは、地代が非常に割高で、更地の状態で最有効使用の建物を想定し、この建物を利用することによって得られる収益よりも地代収入を得た方が長期的にみて得策だと考えられるからでした。
以上のようにこのような例外的ケースは、土地の賃貸借契約が契約当事者間で自由に取り交わされ、かつ、賃貸借契約において一旦、当事者間で合意がなされると正当な事由等が無い限り、賃料の改定には困難が伴うため、発生するものと考えられます。
まとめ
この上記、例外的なケースを踏まえたうえで、不動産の鑑定評価において学ぶべき教訓があります。
不動産の鑑定評価においては、原則的、一般的な考え方を理解することもちろん重要ですが、それが本当に正しいのか、真実なのかという姿勢を常に持っている必要があります。そうでなければ上記のような例外的なケースは見落としてしまい、結局、依頼者の利益を逸することになってしまいかねません。
世の中に不動産鑑定士が必要とされるのかといえば、取引市場をぼんやり眺めていただけでは、不動産の真の価値を知ることは不可能であって、簡単に価値判断できてしまう様な場合には、鑑定評価のニーズはなく、一般の人々では価値判断が困難なケースにこそニーズがあるからだと思います。
もちろん、証拠書面としての鑑定評価が必要だというニーズはありますが、不動産鑑定士だからこそ不動産の経済価値を知ることができた、というニーズを満たせてこそ存在価値があるように思います。
次回は、不動産の鑑定評価において重要な視点の一つ、市場分析について触れていきます。